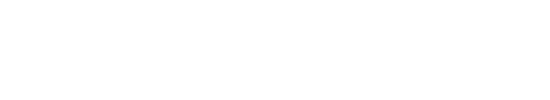Fungiidae クサビライシ科
Cycloseris Milne Edwards & Haime, 1849 マンジュウイシ属
Cycloseris fragilis (Alcock, 1893)
(Figs. 1-15)
Diaseris fragilis Alcock, 1893: 148, pl. 5 fig. 11 [dredged in the Andaman Sea]; Nishihira
2019: 56 (part), 2 skeleton figs.
Fungia patelliformis Boschma, 1923: 136–138, pl. 9, figs. 9, 11, 13–14a, 16–16a.
Cycloseris patelliformis: Veron & Pichon 1980: 115, figs. 184–187; Nishihira & Veron 1995:
237, 2 figs.; Veron 2000: vol. 2, 246, figs. 1–3, 1 skeleton fig.
Diaseris cf. fragilis: Randall & Myers 1983: 17, figs. 337, 338.
Fungia (Cycloseris) fragilis: Hoeksema 1989: 54, figs. 4, 110-121, 614.
Diaseris distorta: Nishihira 1991: 110 (part), lower fig.
Cycloseris fragilis: Hoeksema 2014: 74; Yokochi et al. 2019: 45.
not Diaseris fragilis: Veron & Pichon 1980: 123, figs. 197–201 (= Cycloseris sinensis); Shirai & Sano 1985: 225, fig. 1 (= Cycloseris sinensis); Veron 1986: 327, figs. 4, 5, 1 skeleton fig. (= Cycloseris sinensis); Nishihira 1991: 111, 1 fig. (= Cycloseris sinensis); Nishihira & Veron 1995: 240, 2 figs. (= Cycloseris sinensis); Veron 2000: vol. 2, 250, figs. 1–4, 1 skeleton fig. (= Cycloseris sinensis); Nishihira 2019: 56 (part), 2 underwater figs. (= Cycloseris sinensis).
ウスマンジュウイシ 新称
(図1-15)
ワレクサビライシ: 西平 1991: 110 (一部), 下図.
オオワレクサビライシ: 西平 2019: 56 (一部), 2図 (骨格写真).
図1A–H. CMNH-ZG 00783. 西表島網取湾, 水深 35 m. 2014-08-04. サンゴ体の長径 43.4 mm.
立川浩之採集. 和名基準標本.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: 肋の配列状態.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: 生時のサンゴ体.
図2A–H. MU-IR460. 西表島 (採集地点・水深・採集日不明). サンゴ体の長径 51.4 mm. 奥裕太郎採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の配列状態.
F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
G: 肋の配列状態.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
図3A–H. OCTU-C90045. 西表島網取湾, 水深 40 m. 1990-07-22. サンゴ体の長径 50.5 mm.
横地洋之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の配列状態.
F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
G: 肋の配列状態.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
図4A–H. OCTU-C90043. 西表島網取湾, 水深約 35 m. 1990-07-11. サンゴ体の長径 60.8 mm.
横地洋之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の配列状態.
F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
G: 肋の配列状態.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
図5A–H. OCTU-C90012. 西表島網取湾, 水深 40 m. 1990-06-28. サンゴ体の長径 40.6 mm.
横地洋之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の配列状態.
F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
G: 肋の配列状態.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
図6A–H. OCTU-C90009. 西表島網取湾, 水深 40 m. 1990-06-28. サンゴ体の長径 57.4 mm.
横地洋之採集.
A–C: サンゴ体の上面,側面および下面.
D: 隔壁の配列状態.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: 肋の配列状態.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: サンゴヤドリガニ科の寄生ガニ.
図7A–B. CMNH-ZG 03964a–f. 沖縄本島西沖ナガンヌ島付近, 水深 57 m, ドレッジ採集.
2005-05-22. サンゴ体の長径 7.4–13.5 mm. 広島大学練習船豊潮丸/立川浩之採集.
A: サンゴ体6点の上面.
B: サンゴ体6点の下面.
図8A–H. KS-AMO-166. 奄美大島国直海岸, 水深 42.7 m. 2017-09-13. サンゴ体の長径 31.2 mm.
下池和幸採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の配列状態.
F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: 生時のサンゴ体.
図9A–I. CMNH-ZG 07577a. 奄美大島白浜海岸, 水深 26 m. 2016-01-31. サンゴ体の長径 28.8 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 側面 (2方向) および下面.
E: 生時のサンゴ体.
F: 隔壁の配列状態.
G: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
H: 肋の配列状態.
I: 斜め方向から見た肋の突起列.
図10A–H. CMNH-ZG 06404. 熊本県天草市砂月浦, 水深 24 m. 2011-12-07. サンゴ体の長径 70.4 mm.
深見浩伸採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面 (下面中央部付近に破片からの再生の痕跡が残る).
E: 隔壁の配列状態.
F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
G: 肋の配列状態.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
図11A–H. CMNH-ZG 10284. 高知県大月市橘浦, 水深 14 m. 2009-10-31. サンゴ体の長径 60.9 mm.
横地洋之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の配列状態.
F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
G: 肋の配列状態.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
図12A–I. CMNH-ZG 10285. 高知県大月市橘浦, 水深 14 m. 2009-10-31. サンゴ体の長径 30.8 mm.
横地洋之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 側面 (2方向) および下面.
E: 隔壁の配列状態.
F–G: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
H: 肋の配列状態.
I: 斜め方向から見た肋の突起列.
図13A–H. CMNH-ZG 07379. 小笠原諸島父島, 水深 35 m. 1991-01-18. サンゴ体の長径 69.4 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の配列状態.
F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
G: 肋の配列状態.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
図14A–H. CMNH-ZG 07419a. 小笠原諸島父島列島西島, 水深 90 m, ドレッジ採集. 1991-11-23.
サンゴ体の長径 34.7 mm. 永井誠二採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の配列状態.
F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
G: 肋の配列状態.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
図15A–J. CMNH-ZG 07414a–b. 小笠原諸島父島, 水深 20 m. 1991-01-24. A–H:
CMNH-ZG 07414a.サンゴ体の長径 23.5 mm. I–J: CMNH-ZG 07414b.サンゴ体の長径 22.9 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 側面 (2方向) および下面.
E: 隔壁の配列状態.
F: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
G: 肋の配列状態.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
I: サンゴ体の上面.
J: サンゴ体の下面.
図の撮影は図8Hのみ下池和幸、他は全て立川浩之. 骨格拡大写真のスケールは一目盛 5 mm.
形態:成体のサンゴ体は自由生活性で通常は単口性。サンゴ体は通常型またはワレクサビライシ型のいずれかの形状。観察に用いた通常型の標本の長径は 2.9~7.1 cm
(N=11) (Hoeksema (1989) の検討標本は最大 15.0 cm),ワレクサビライシ型のサンゴ体の半径は最大 4.0 cm
(N>80)。
通常型のサンゴ体の輪郭はほぼ円形であるが (図1, 2, 8, 14)、成長途中の破損・再生により楕円形または不規則な輪郭となることがある (図3,
10, 13)。破損・再生をしていないサンゴ体では長径は短径の1.01~1.11倍程度。サンゴ体は薄い円盤状で、上面中央部で低次隔壁が立ち上がるため口の周辺が盛り上がって見える。サンゴ体下面はほぼ平面状。口は上面中央に位置する。軸柱は細かいトラベキュラの集合からなり、サンゴ体長径方向に延びる楕円形を呈する。軸柱の長径はサンゴ体長径の7~15%程度。軸柱の長軸延長線方向
(=サンゴ体の長軸方向) に位置する隔壁は軸柱付近から斜めに立ち上がる。
ワレクサビライシ型のサンゴ体は扇形~楔形の小片の集合からなり、再生の段階により様々な形態となる (図4–7, 9, 11, 12, 15)。サンゴ体は薄く、口の周辺の隔壁がやや高まることがある
(図9, 11)。軸柱から放射状に延びる面を破断面として自切が起こるため、軸柱部が脱落して口が不明瞭だったり、再生に伴って一時的に複数の口が観察されたりすることも多い。
隔壁は隙間を持って配列し、薄く直線状で、大型 (相対的に低次) の隔壁と小型 (相対的に高次) の隔壁の高さの差は大きい。サンゴ体周縁部付近では隔壁の高さが「高–低–中–低–高」の周期で配列することが多い。触手葉は形成されない。隣接する隔壁間の間隙は大きく、骨格標本では隔壁間の複合シナプティキュラが明瞭に観察される。隔壁の縁辺には細かい三角形の鋸歯が並ぶ。鋸歯の数は 1 cm あたり38~62程度。隔壁側面は微細な顆粒で覆われ、多くの場合顆粒は隔壁縁辺と垂直に並ぶ。
肋は細いが明瞭で、下面周縁部から中央部付近までほぼ直線状に連なる。肋は大小のものが交互に配列し、特にサンゴ体周縁部付近ではその差が明瞭である。肋の縁辺には尖った三角形の突起が一列の鋸歯状に並ぶ。肋縁辺の突起の数は 1 cm あたり37~70程度。サンゴ体壁に穴はあかない。
生時の色彩は茶褐色~淡褐色で、放射状に淡色の模様がみられたり、口や大型隔壁の内縁部が淡色になることがある (図8H, 9E)。
識別点:本種の通常型のサンゴ体のものは、Cycloseris costulata スジマンジュウイシおよび C. distorta ユガミマンジュウイシの通常型で盛り上がりの少ないものと類似する。スジマンジュウイシとは、本種の方がサンゴ体が薄く肋の配列が明瞭に大小交互になること
(スジマンジュウイシのサンゴ体は通常厚みのある円盤状で、肋は同大か大小の差がある場合もわずか) などで識別される。ユガミマンジュウイシとは、本種は隔壁が薄く複合シナプティキュラが明瞭に観察され、肋が明瞭に大小交互に配列し、低次隔壁が口の周辺で立ち上がること
(ユガミマンジュウイシでは隔壁がやや厚く複合シナプティキュラが明瞭に観察されないことが多く、肋は同大か大小の差がある場合もわずかで、口の周辺の低次隔壁はあまり立ち上がらない)
などで識別される。 日本産未記録の C. boschmai および C. vaughani はいずれも本種と類似した薄いサンゴ体を持つ種であるが、両種とも他の肋より明瞭に突出する大型の肋が周期的に形成される (本種は大小の肋が交互に並ぶが、明瞭に突出した肋は持たない)
ことで識別される (Hoeksema 1989, 2014)。
ワレクサビライシ型の形態をとる日本産の種の中では、本種は隔壁が薄く隔壁間の間隙が大きいため複合シナプティキュラが明瞭に観察されることや、隔壁縁辺の鋸歯が整った三角形であること、裏面の肋が明瞭に大小交互に配列することで類似種と識別される。生時
(特に触手を伸ばした状態) には類似種との識別が困難なことも少なくないため、正確な同定のためには骨格標本を観察することが望ましい。
 分布と生態:これまでのマンジュウイシ類・ワレクサビライシ類の日本からの報告のうち、西平・Veron (1995) による西表島産の C. patelliformis および西平 (1991) による西表島産の Diaseris distorta の写真はいずれも本種と認められる。これまでのところ、本研究会および執筆者の調査では八重山諸島の西表島、奄美諸島の奄美大島・加計呂麻島、沖縄諸島のナガンヌ島、熊本県の天草、高知県の大月、和歌山県の串本、小笠原諸島の父島列島から標本が得られている。本種は本州温帯域
(和歌山県・高知県・熊本県) 以南の海域に広く分布するものと思われる。波当たりの弱い礁斜面下部や、やや内湾の深場の砂泥底などの環境に生息する。外洋に面した礁斜面下部の深所
(水深 50–90 m) からドレッジにより大量の標本が採集されたこともある。
分布と生態:これまでのマンジュウイシ類・ワレクサビライシ類の日本からの報告のうち、西平・Veron (1995) による西表島産の C. patelliformis および西平 (1991) による西表島産の Diaseris distorta の写真はいずれも本種と認められる。これまでのところ、本研究会および執筆者の調査では八重山諸島の西表島、奄美諸島の奄美大島・加計呂麻島、沖縄諸島のナガンヌ島、熊本県の天草、高知県の大月、和歌山県の串本、小笠原諸島の父島列島から標本が得られている。本種は本州温帯域
(和歌山県・高知県・熊本県) 以南の海域に広く分布するものと思われる。波当たりの弱い礁斜面下部や、やや内湾の深場の砂泥底などの環境に生息する。外洋に面した礁斜面下部の深所
(水深 50–90 m) からドレッジにより大量の標本が採集されたこともある。
新称和名:D. fragilis (= C. fragilis) に対する和名としては、これまでオオワレクサビライシ (またはアクロバットサンゴ) が用いられてきたが (白井・佐野 1985, 西平 1988, 1991, 内田・福田 1989, 西平・Veron 1995 など)、これらの大部分は C. sinensis シナマンジュウイシの誤同定であり、正しく C. fragilis に適用されたものは、西平 (2019)の骨格標本写真のみと思われる (本WEB図鑑のシナマンジュウイシおよび本種のページのシノニムリストを参照)。他方、西平・Veron (1995) が C. patelliformis として示した西表島産の写真のサンゴは本種と思われるが、和名は与えられなかった。以上のことから、C. fragilis には新称和名が必要と考えられる。本種はマンジュウイシ属の中でもサンゴ体の厚みが薄い種であり、またその隔壁も他種と比べて薄い。この特徴に因み、新称和名ウスマンジュウイシを提唱する。新称和名の基準標本は CMNH-ZG 06783 (図1:八重山諸島西表島網取湾、水深 35 m で採集) である。
和名提唱日:2025-09-28.
備考: 西表島網取湾で採集された標本 OCTU-C90009 の上面に、Cryptochiridae サンゴヤドリガニ科のカニ1個体が寄生しているのが確認された
(Fig. 6A, H)。乾燥標本のためカニを取り出しての種の同定は行えなかったが、宿主がマンジュウイシ属であることから、Mykescola syzygia (van der Meij, 2015) の可能性がある (van der Meij 2025, van der Meij et al. 2015)。
引用文献:
Alcock A (1893) On some newly-recorded corals from the Indian Seas. J Asiat Soc Bengal Nat Hist 62: 138-149. [BHL]
Boschma H (1923) The Madreporaria of the Siboga Expedition IV. Fungia patella. Siboga-Expedition (Brill, Leiden). XVId: 129-148, pls. 9-10.
Hoeksema BW (1989) Taxonomy, phylogeny and biogeography of mushroom corals (Scleractinia Fungiidae). Zool Verh 254: 1-295. [ResearchGate]
Hoeksema BW (2014) The “Fungia patella group” (Scleractinia, Fungiidae) revisited with a description of the mini mushroom coral Cycloseris boschmai sp. n. Zookeys. 17: 57–84. [ZooKeys]
西平守孝 (1991) フィールド図鑑 造礁サンゴ 増補版. 東海大学出版会, 東京.
西平守孝 (2019) 有藻性サンゴ類属の同定練習帳. 沖縄美ら島財団総合研究センター, 本部町.
西平守孝・Veron JEN (1995) 日本の造礁サンゴ類. 海游社, 東京.
Randall RH, Myers RF (1983) Guide to the coastal resources of Guam, vol. 2. The corals. University of Guam Press.
白井祥平・佐野芳康 (1985) 石垣島周辺海域サンゴ礁学術調査報告書. 太平洋資源開発研究所, 石垣.
内田紘臣・福田照雄 (1989) 沖縄海中生物図鑑 第9巻 サンゴ. 新星図書出版, 浦添.
van der Meij SET (2025) Mykescola gen. nov., a new genus for two coral-dwelling gall crab species (Decapoda: Cryptochiridae) inhabiting Fungiidae Dana, 1846 corals. Zootaxa 5631: 594-600.
van der Meij SET, Fransen CHJM, Pasman LR, Hoeksema BW (2015) Phylogenetic ecology of gall crabs (Cryptochiridae) as associates of mushroom corals (Fungiidae). Ecol Evol 5: 5770-5780. [Wiley OL Lib]
Veron JEN (1986) Corals of Australia and the Indo-Pacific. Angus & Robertson Publication, North Ryde, NSW.
Veron JEN (2000) Corals of the world, vol. 2. Australian Institute of Marine Science, Townsville.
Veron JEN, Pichon M (1980) Scleractinia of eastern Australia, part III. Families Agariciidae, Siderastreidae, Fungiidae, Oculinidae, Merulinidae, Mussidae, Pectiniidae, Caryophylliidae, Dendrophylliidae. Australian Institute of Marine Science, Townsville. [BHL]
横地洋之・下池和幸・梶原健次・野村恵一・北野裕子・松本尚・島田剛・杉原薫・鈴木豪・立川浩之・山本広美・座安佑奈・木村匡・河野裕美 (2019)
西表島網取湾の造礁サンゴ類. 西表島研究 2018, 東海大学沖縄地域研究センター所報 36-69.
執筆者:立川浩之
Citation:
更新履歴:
2025-09-28 公開