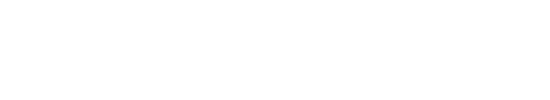Fungiidae クサビライシ科
Cycloseris Milne Edwards & Haime, 1849 マンジュウイシ属
Cycloseris tenuis (Dana, 1846)
(Figs. 1-10)
Fungia tenuis Dana, 1846: 290 [Pacific Ocean, and probably the Paumotu Archipelago]; 1849: pl. 18, fig. 1.
Fungia erosa: Yabe & Sugiyama 1941: 76, pl. 64, figs. 4-4d.
Cycloseris costulata: Randall & Myers 1983: 17, figs. 333, 334.
Cycloseris vaughani: Uchida & Fukuda 1989: 19, 1 fig.; Nishihira 1991: 252, 1 fig.; Nishihira & Veron 1995: 238, 2 figs.; Kameda, Mezaki & Sugihara 2013: 27, 90, 3 figs. Nomura, Uchida & Fukuda 2008: 196.
Fungia (Cycloseris) tenuis: Hoeksema 1989: 70, figs. 6, 158–175.
Cycloseris tenuis: Claereboudt 1991: 21; Hoeksema 2014: 73; Sugihara et al. 2015: 93, 3 figs.; Nomura 2016: 11, figs. A–F; Nomura et al. 2016: 9, 19; Yokochi et al. 2019: 45.
? Cycloseris tenuis: Veron 2000: vol. 2, 244, fig. 1, 1 skeleton fig.
マンジュウイシモドキ 内田・福田, 1989
(図1-10)
マンジュウイシモドキ 内田・福田, 1989: 19, 1 図 (Cycloseris vaughani として); 西平 1991: 252, 1 図 (Cycloseris vaughani として); 野村・目崎 2005: 33, 図20 (中央) (Cycloseris vaughani として); 野村・内田・福田 2008: 196(Cycloseris vaughani として); 野村ら 2008: 196 (Cycloseris vaughani として); 亀田・目崎・杉原 2013: 27, 90, 3図 (Cycloseris vaughani として); 杉原ら 2015: 93, 3図; 野村 2016: 11, 図A–F; 野村ら 2016: 9, 19; 横地ら 2019:
45.
マンジュウイシモドキの和名は、内田・福田 (1989) により Cycloseris vaughani に同定された標本に与えられた。しかしながら彼らの図示した写真のサンゴ体は下面の肋の形状から C. vaughani ではなく C. tenuis と同定される。このため、杉原ら (2015) はマンジュウイシモドキの和名を担う種は C. vaughani ではなく C. tenuis であるとした。本WEB図鑑もこの扱いに従い、C. tenuis の和名をマンジュウイシモドキとする。
図1A–H. CMNH-ZG 00390. 八重山諸島黒島, 水深 15 m. 2000-02-16. サンゴ体の長径 63.0 mm.
野村恵一・立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: サンゴ体下面の肋の配列.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: 生時のサンゴ体.
図2A–H. CMNH-ZG 06844. 西表島網取湾, 水深 10 m. 2014-08-05. サンゴ体の長径 51.5 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: サンゴ体下面中央部付近の肋の配列.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: 生時のサンゴ体.
図3A–H. CMNH-ZG 06970. 宮古諸島八重干瀬, 水深 20 m. 2014-10-25. サンゴ体の長径 53.8 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: サンゴ体下面の肋の配列.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: 生時のサンゴ体.
図4A–H. CMNH-ZG 06998. 宮古諸島八重干瀬, 水深 12 m. 2014-10-25. サンゴ体の長径 47.9 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: サンゴ体下面の肋の配列.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: 生時のサンゴ体.
図5A–H. CMNH-ZG 08577. 奄美諸島喜界島, 水深 15 m. 2011-01-23. サンゴ体の長径 51.1 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: サンゴ体下面の肋の配列.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: 生時のサンゴ体.
図6A–H. CMNH-ZG 08577. 奄美大島大和村国直, 水深 30 m. 2017-09-13. サンゴ体の長径 61.8 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: サンゴ体下面の肋の配列.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: 生時のサンゴ体.
図7A–H. CMNH-ZG 06064. 吐噶喇列島中之島, 水深 10 m. 2010-07-06. サンゴ体の長径 54.7 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: サンゴ体下面中央部付近の肋の配列.
G: サンゴ体下面周縁部付近の肋の配列.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
図8A–H. CMNH-ZG 07397. 小笠原諸島父島, 水深 20 m. 1990-08-21. サンゴ体の長径 87.0 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: サンゴ体下面の肋の配列.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: 生時のサンゴ体.
図9A–H. CMNH-ZG 07398. 小笠原諸島父島列島西島, 水深 20 m. 1990-09-15. サンゴ体の長径
65.1 mm. 立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: サンゴ体下面中央部付近の肋の配列.
G: サンゴ体下面周縁部付近の肋の配列.
H: 斜め方向から見た肋の突起列.
図10A–H. CMNH-ZG 07399. 小笠原諸島兄島, 水深 20 m. 1990-10-06. サンゴ体の長径 67.0 mm.
立川浩之採集.
A–D: サンゴ体の上面, 斜め上面, 側面および下面.
E: 隔壁の鋸歯と側面の顆粒列.
F: サンゴ体下面の肋の配列.
G: 斜め方向から見た肋の突起列.
H: 生時のサンゴ体.
図の撮影は全て立川浩之. 骨格拡大写真のスケールは一目盛 5 mm.
形態: 成体のサンゴ体は自由生活性で通常は単口性。日本産の標本でワレクサビライシ型のサンゴ体は観察されていない。観察に用いた標本の長径は 4.4~8.7 cm
(N=20) (Hoeksema (1989) の検討標本は最大 9.0 cm)。サンゴ体の輪郭は整った円形からわずかに楕円形。長径は短径の1.01~1.09倍程度。サンゴ体は厚みのある円盤状で、通常上面全体がゆるやかに盛り上がるが、サンゴ体により口の周辺のみがやや盛り上るものもある
(図6, 10)。サンゴ体下面はほぼ平面状。口は上面中央に位置し、細かいトラベキュラの集合からなるサンゴ体長径方向に長い軸柱を持つ。軸柱の長径はサンゴ体長径の11~19%程度。軸柱の長軸方向に位置する隔壁は軸柱付近から比較的急角度で立ち上がるため、外観上口が短く見える。
隔壁はやや隙間を持って配列し、直線状からやや蛇行し、大型 (相対的に低次) の隔壁と小型 (相対的に高次) の隔壁が交互に並ぶ。触手葉は形成されないことが多いが、サンゴ体により弱い触手葉が形成されることがある
(図4, 8, 9, 10)。隔壁の縁辺には細かい三角形の鋸歯が並ぶ。鋸歯の数は 1 cm あたり25~50程度。隔壁側面は微細な顆粒で覆われ、多くの場合顆粒は隔壁縁辺と垂直に並ぶ。
肋は明瞭で、下面周縁部から中央部付近までほぼ直線状に連なる。肋は不揃いで大きさの差が大きく、大型の肋はサンゴ体周縁部にかけて明瞭に突出する。肋の縁辺には様々な大きさの尖った突起が並び、大型の肋では突起が癒合したり突起上に尖った顆粒が生じたりして不規則な形となる。突起が不ぞろいなため同一サンゴ体でも肋の部位による突起数の変異は大きいが、突起数は概ね 1 cm
あたり12~38程度。サンゴ体壁に穴はあかない。
生時の色彩は茶褐色~暗褐色で、上面が不規則または放射状のまだら模様となることが多い。
識別点:本種は肋の形態がマンジュウイシ属の中では特異的であり、下面を観察すれば他種と混同することはない。上面の形態は C. costulata スジマンジュウイシと非常によく似るが、下面の形態を見れば識別は容易である。 その他のマンジュウイシ属の種では、C. vaughani および C. boschmai の2種が周期的に発達した大型の肋 (低次肋) を持つ。これらの2種はいずれも本種に比べてサンゴ体が薄いことのほか、C. vaughani では低次肋が薄く立ち上がり、肋縁辺の突起が極めて細かく (1 cm あたりの突起数は40~80)、肋の側面に縁辺と垂直に顆粒が並ぶことで、C. boschmai では低次肋が厚くサンゴ体周縁より突出し、縁辺の突起が細かい (1 cm あたり 20~70) ことで本種と識別される
(Hoeksema 1989, 2014)。
 分布と生態:日本では、八重山諸島海域 (亀田ら 2013) および西表島 (西平・Veron 1995, 横地ら 2019)、沖縄諸島の伊良部島 (西平・Veron
1995)、薩南諸島の種子島 (杉原ら 2015)、高知県大月 (野村・目崎 2005)、和歌山県串本 (野村 2016, 野村ら2008,
2016)、三重県浜島 (Yabe & Sugiyama 1941) などから知られている。これまでのところ、本研究会および執筆者の調査では八重山諸島の石西礁湖・西表島、宮古諸島の宮古島・八重干瀬、奄美諸島の奄美大島・加計呂麻島・喜界島、吐噶喇列島の中之島、薩南諸島の種子島、和歌山県串本および小笠原諸島の父島列島から標本が得られている。波当たりの弱い礁池内や礁斜面、外洋に面した斜面のやや深場など様々な環境の場所に生息する。
分布と生態:日本では、八重山諸島海域 (亀田ら 2013) および西表島 (西平・Veron 1995, 横地ら 2019)、沖縄諸島の伊良部島 (西平・Veron
1995)、薩南諸島の種子島 (杉原ら 2015)、高知県大月 (野村・目崎 2005)、和歌山県串本 (野村 2016, 野村ら2008,
2016)、三重県浜島 (Yabe & Sugiyama 1941) などから知られている。これまでのところ、本研究会および執筆者の調査では八重山諸島の石西礁湖・西表島、宮古諸島の宮古島・八重干瀬、奄美諸島の奄美大島・加計呂麻島・喜界島、吐噶喇列島の中之島、薩南諸島の種子島、和歌山県串本および小笠原諸島の父島列島から標本が得られている。波当たりの弱い礁池内や礁斜面、外洋に面した斜面のやや深場など様々な環境の場所に生息する。
和名の由来:内田・福田 (1989) は和名マンジュウイシモドキの由来を明示していないが、本種の形態が C. cyclolites マンジュウイシと類似していることに基づき命名されたものと思われる。ただし、上記の識別点の項で述べたように、本種はマンジュウイシよりもスジマンジュウイシにより類似している。
引用文献:
Claereboudt MR (1991) 慶良間列島におけるクサビライシ類. みどりいし2: 20–23. [阿嘉島臨海研究所]
Dana JD (1846) Zoophytes. United States exploring expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes, U.S.N. Vol. VII. Lea and Blanchard, Philadelphia. [Smithson Lib]
Hoeksema BW (1989) Taxonomy, phylogeny and biogeography of mushroom corals (Scleractinia Fungiidae). Zool Verh 254: 1-295. [ResearchGate]
Hoeksema BW (2014) The “Fungia patella group” (Scleractinia, Fungiidae) revisited with a description of the mini mushroom coral Cycloseris boschmai sp. n. Zookeys. 17: 57–84. [ZooKeys]
亀田和成・目崎拓真・杉原薫 (2013) 黒島研究所収蔵造礁サンゴ目録第2版. 日本ウミガメ協議会付属 黒島研究所, 竹富町. [日本ウミガメ協議会付属黒島研究所]
西平守孝 (1991) フィールド図鑑 造礁サンゴ 増補版. 東海大学出版会, 東京.
西平守孝・Veron JEN (1995) 日本の造礁サンゴ類. 海游社, 東京.
野村恵一 (2016) 串本産有藻性イシサンゴ類図鑑. Ⅱ ナミフウセン亜目. マリンパビリオン 特別号6. [串本海中公園]
野村恵一・深見裕伸・座安佑奈・島田剛 ・ 北野裕子・横地洋之・下池和幸・立川浩之・奥裕太郎・鈴木豪・梶原健次 (2016) 串本産有藻性イシサンゴ類相の再整理. マリンパビリオン特別号 4: 1-20. [串本海中公園]
野村恵一・内田紘臣・福田照雄 (2008) 串本産造礁サンゴ類の変遷. 南紀生物 50: 191-200.
Randall RH, Myers RF (1983) Guide to the coastal resources of Guam, vol. 2. The corals. University of Guam Press.
杉原薫・野村恵一・横地洋之・下池和幸・梶原健次・鈴木豪・座安佑奈・出羽尚子・深見裕伸・北野裕子・松本尚・目﨑拓真・永田俊輔・立川浩之・木村匡 (2015) 日本の有藻性イシサンゴ類. 種子島編.国立環境研究所生物・生態系環境研究センター, つくば. [国立環境研究所]
内田紘臣・福田照雄 (1989) 沖縄海中生物図鑑 第9巻 サンゴ. 新星図書出版, 浦添.
Veron JEN (2000) Corals of the world, vol. 2. Australian Institute of Marine Science, Townsville.
Yabe H, Sugiyama T (1941) Recent reef-building corals from Japan and the South Sea Islands under the Japanese mandate. II. Sci Rep Tohoku Imp Univ 2nd Ser Geol, spec vol 2: 67-91, pls. 60-104. [東北大学]
横地洋之・下池和幸・梶原健次・野村恵一・北野裕子・松本尚・島田剛・杉原薫・鈴木豪・立川浩之・山本広美・座安佑奈・木村匡・河野裕美 (2019)
西表島網取湾の造礁サンゴ類. 西表島研究 2018, 東海大学沖縄地域研究センター所報 36-69.
執筆者:立川浩之
Citation:
更新履歴:
2025-09-28 公開