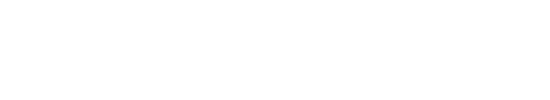Acroporidae ミドリイシ科
Montipora コモンサンゴ属
Montipora capricornis Veron, 1985
(Fig. 1)
Montipora sp. 2: Veron & Wallace 1984: 42, figs. 94-97.
Montipora capricornis Veron, 1985: 149, fig. 2 [Llewellyn Reef, GBR]; Veron 1986: 102, 2 figs., 1 skeleton fig.; Veron 2000: vol. 1, 80, figs. 1-5, 1 skeleton sketch.
Montipora cf. capricornis: Nomura & Suzuki 2015: 6, fig. 64.
Montipora sp. AIMAIIBO sensu Kajiwara et al. 2020: 78.
アイマイイボコモンサンゴ 野村・鈴木, 2015
(図1)
アイマイイボコモンサンゴ 野村・鈴木, 2015: 6, 図64 (Montipora cf. capricornis として).; 梶原ら 2020: 78 (Montipora sp. AIMAIIBO として).
図1. アイマイイボコモンサンゴ. Fig. 1. Montipora capricornis Veron, 1985.
A-H. SMP-HC 2854 , 和名基準標本. 宮古諸島宮古島世渡崎沖フゥ・ナガル, 水深 17 m. 2015-07-01: A, B. 群体; D. サンゴ体上面; D-F. 同, 個体とその周囲; G. サンゴ体下面; H. 同, 個体とその周囲.
定規の目盛り: 1 mm. スケールバー: 1 mm. 写真: 野村恵一撮影.
形態:群体は複葉状で葉状部は渦を巻く。調査した群体は小型で、長径は 15 cm である。葉状部はやや薄く、厚さは縁で 3 mm、末縁から 5 cm の距離で 5 mm である。上面は顕著な大型突起を欠く。
サンゴ体上面では共骨は霜柱状突起を含む微小突起を欠く。共骨上では個体周囲の共骨の一部が隆起した疣状突起が形成されるが、形状や大きさ、分布は不均一である。疣状突起の短径は平均 2.0 mm、最大 3.4 mm、平均高は 1.7 mm、最大 3.4 mmである。疣状突起の高幅比
(平均高/平均短径) は 0.85 で、高さは短径よりも小さい。疣状突起は短径が 3 mm を超えると、上半部に生じた個体によって分割される。疣状突起はしばしば互いに接合して短いコリンを形成する。コリンの平均幅は 1.7 mm、最大幅は 2.4 mm、平均高は 2.2 mm である。コリンならびに疣状突起はサンゴ体縁部において破線状の放射列を形成し、さらに縁から約 1 cm の所に共骨と共に隆起した1条の同心円列を形成する。共骨は個体周囲で不規則に隆起して不完全な個体壁を形成する傾向がある。
個体の分布には粗密があるが、たいてい個体間隔は個体1個分である。個体は共骨もしくは棘の中にわずかに窪み、サンゴ体縁部を除いて共骨面に対して垂直方向を向く。莢径は平均 0.8 mm である。隔壁は準板状もしくは鋸歯状を成し、方向隔壁を含む1次隔壁は莢奥中心で互いに接近するか部分的に接合して弱い軸柱を形成する。方向隔壁は莢開口面から突出し、長さは平均 0.8R である。1次隔壁は完全・規則的、時にやや突出し、長さは平均 0.7R である。2次隔壁は不完全・不規則で、長さは平均 0.3R である。莢壁は明瞭で、共骨面より突出しない。裸地帯はやや不明瞭である。
共骨表面の目合いは平均 0.2 mm、網目はフレームとほぼ同幅で、表面の肌理はやや粗い。棘の長さは平均 0.25 mm、最長 0.4 mm、棒状もしくは薄片状を成し、後者の場合は上縁が複数の尖端に分かれる。棘の上縁は顆粒状突起が弱く発達する。
サンゴ体下面ではエピテカが不均一 (斑状) に発達し、共骨表面は滑らかである。個体は疎らに分布し、共骨面より突出せず、莢径は平均 0.7 mm である。
生時の色彩は共肉が灰褐色、触手は淡褐色を呈する。
識別点:本種の疣状突起と粒状突起を併せ持つ特徴は Montipora sp. MIDAREIBO ミダレイボコモンサンゴと共有するが、両者は群体形の違い (前者は幅広い葉状部を持つのに対し、後者は短い板状部を持つものの葉状部を欠く)
で区別される。
和名の由来:疣状突起が低く不明瞭である特徴に因む。和名基準標本は SMP-HC 2854 (宮古島産)。
備考:M. capricornis のホロタイプとパラタイプとはサンゴ体の形が大きく異なり、前者は直径 18 cm の平板状であるのに対し、後者は高さ 14 cm の柱状である。この両タイプ間における著しい形状の相違は、両者の種同一性に疑問を生じさせる。しかしながら、原記載では両形は同所的に産し、しかも両形が合わさった群体形も認められることが記されている。宮古島産の標本と本種のホロタイプとの間にいくつかの形態差が認められたが
(前者は疣状突起が後者よりも発達する、前者は疣状突起とコリンが破線状の放射列を形成するのに対し後者では放射列は認められない、前者の莢径は後者よりも小さい)、本稿ではこれらの形態差は種内変異の範囲内であると判断した。なお、ソロモン諸島がタイプ産地である
M. guppyi Bernard, 1897 と M. capricornis のホロタイプとの間には本質的な形態差が認められないため、両者のシノニム関係については検討の余地が持たれる。
引用文献:
梶原健次・北野裕子・木村匡・座安佑奈・島田剛・下池和幸・杉原薫・鈴木豪・立川浩之・出羽尚子・野村恵一・松本尚・山本広美・横地洋之 (2020) 宮古諸島造礁サンゴ目録. In: 宮古島市史編さん委員会(編) 宮古島市史第3巻自然編第1部宮古の自然(別冊). 宮古島市教育委員会, 宮古島市, pp 73-91.
野村恵一・鈴木豪 (2015) コモンサンゴ類の同定の話(28), 国内産種の紹介16, イボコモンサンゴ種群(3). マリンパビリオン特別号3. [串本海中公園]
Veron JEN (1985) New Scleractinia from Australian coral reefs. Rec West Aust Mus 12: 147-183. [Western Australian Museum]
Veron JEN (1986) Corals of Australia and the Indo-Pacific. Angus & Robertson Publication, North Ryde, NSW.
Veron JEN (2000) Corals of the world, vol. 1. Australian Institute of Marine Science, Townsville.
Veron JEN, Wallace CC (1984) Scleractinia of eastern Australia, part V.
Family Acroporidae. Australian Institute of Marine Science, Townsville.
[BHL]
執筆者:野村恵一・鈴木豪
Citation:
更新履歴:
2025-05-04 公開